相続でまず押さえるべきは、誰が法定相続人になるのか、そしてどの順番・割合で相続するのかです。配偶者は常に相続人となり、子(直系卑属)・直系尊属・兄弟姉妹は順位に従って相続人となります。この記事では民法のルールを、表や具体例でわかりやすく説明します。
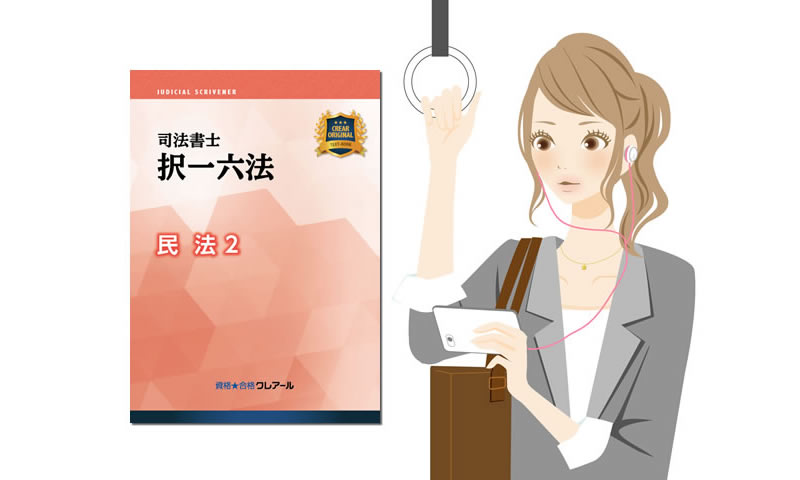
また、代襲相続(子が先に亡くなっている等の場合に孫が代わる制度)や、半血兄弟の取り扱い、胎児・非嫡出子・養子の相続、事実婚パートナーの注意点など、迷いやすい論点も一気に整理。最新の公的情報にあたりながら、実務で役立つ要点をまとめました。
法定相続人とは(基本の考え方)
法定相続人とは、民法が定める「遺産を承継できる人」の範囲です。配偶者は常に相続人であり、これに加えて血族相続人(子→直系尊属→兄弟姉妹)が順位に従って相続人となります。血族相続人がいなければ、配偶者が単独で相続します。
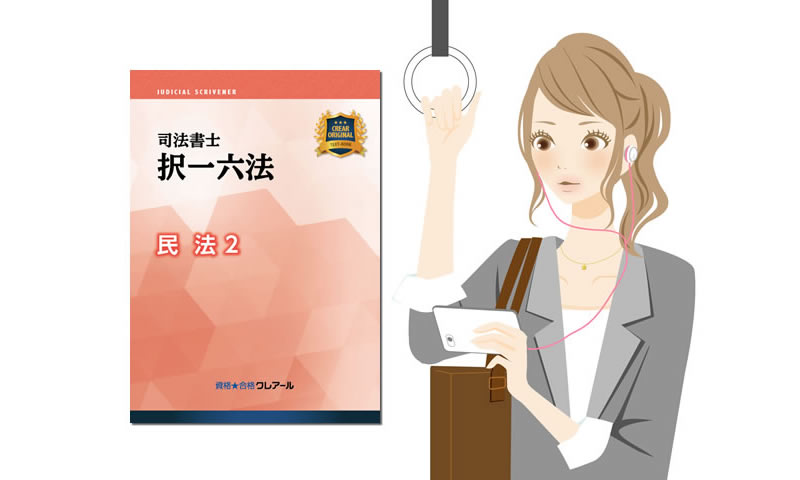
同居中のパートナー(事実婚・内縁)は、民法上の配偶者に当たらないため法定相続人には含まれません(遺言等での備えが不可欠)。また、「相続放棄」をした人は、はじめから相続人でなかったものと扱われます。
相続順位(第1〜第3)と配偶者の位置づけ
順位は「第1順位:子(直系卑属) → 第2順位:直系尊属 → 第3順位:兄弟姉妹」の順。配偶者は常に相続人で、該当する血族相続人がいる場合はその者と同順位で相続人となります。
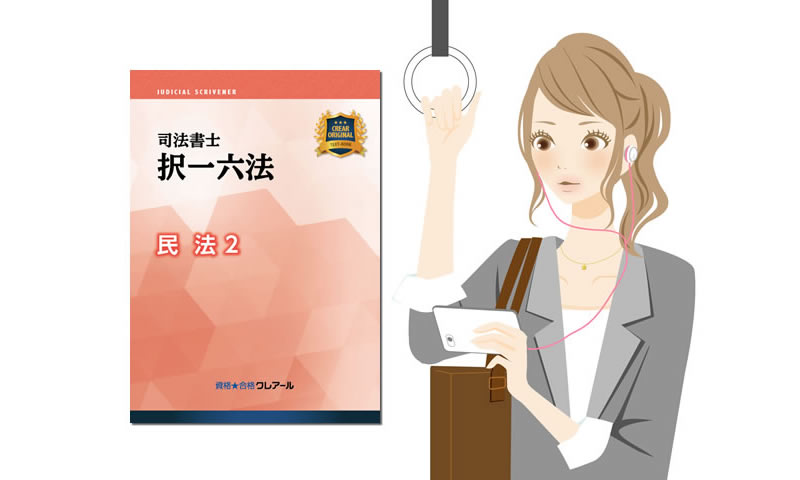
第1順位がいると第2・第3順位には出番がありません。たとえば「配偶者+子」がいれば、親や兄弟姉妹は相続人になりません。例外・特殊ケースはのちほど詳説します。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
第1順位:子・直系卑属(代襲相続あり)
子が相続人です。子がすでに死亡・欠格・廃除の場合は、その子(孫)が代襲相続し、さらに孫も同様の場合は再代襲が無制限に続きます(ひ孫…)。相続放棄は代襲原因ではない点に注意。
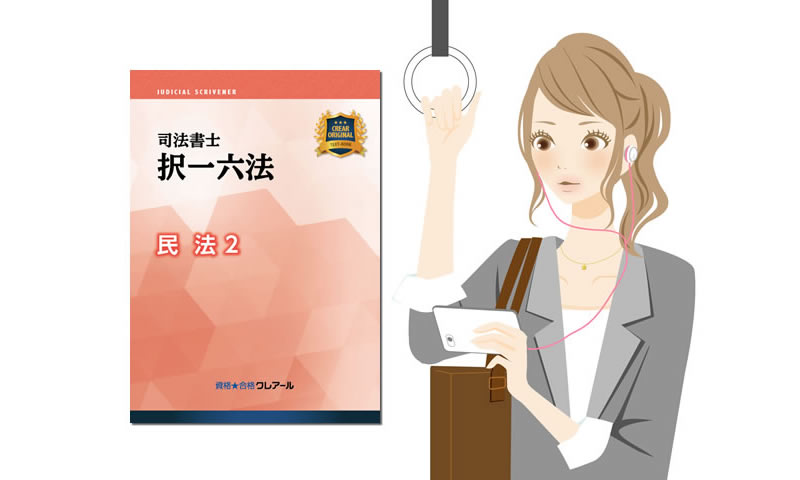
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
子がいない場合に限り、父母・祖父母などの直系尊属が相続人になります。複数いれば同順位者で均等に分けます。
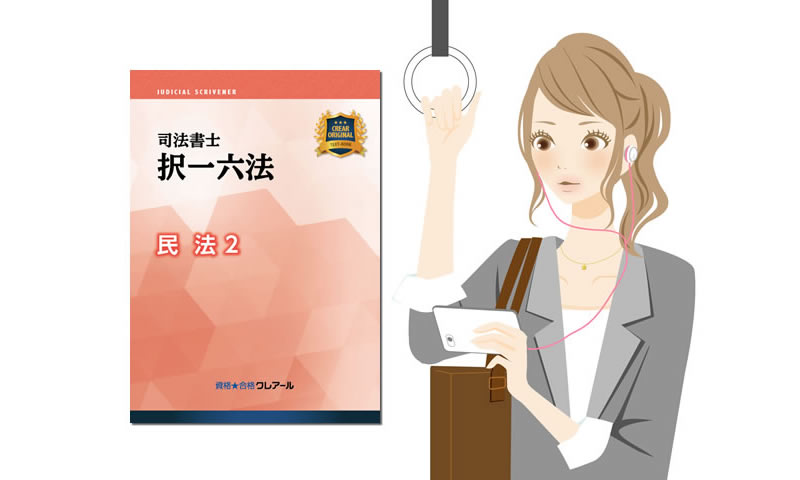
第3順位:兄弟姉妹(甥姪の代襲は一代限り)
子も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その子(甥・姪)が一代限りで代襲相続します(甥姪の子へは再代襲なし)。
法定相続分(相続割合)の早見表
合意で自由に分けることも可能ですが、合意に至らない場合などの基準となるのが「法定相続分」です。配偶者と誰が一緒に相続人になるかで割合が決まります。
下表は民法900条に基づく代表パターンの要点です(同順位が複数いる場合は均等割。半血兄弟姉妹は全血の1/2)。
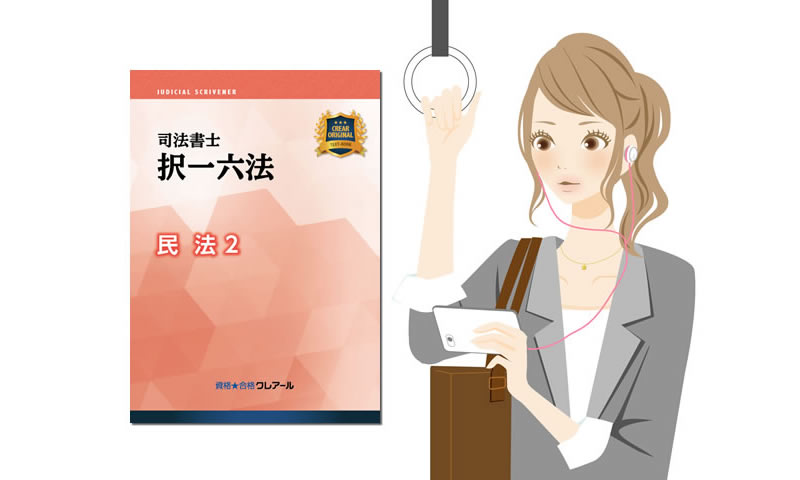
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | その他相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全体で1/2(人数で等分) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全体で1/3(人数で等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4(人数で等分)※半血は全血の1/2 |
| 配偶者のみ(血族なし) | 全部 | — |
ケース別:家族構成でみる相続人の決まり方
家族構成によって、誰が相続人になるか・どの割合かが変わります。以下は代表例です(法定相続人が確定しない場合は家庭裁判所の手続に進むことがあります)。

なお、相続人がいない・わからない場合には「相続人不存在」の手続があり、相続財産管理人の選任・公告・特別縁故者への分与を経て、残余が国庫に帰属します。

| 家族構成の例 | 相続人 | メモ |
|---|---|---|
| 配偶者・子2人 | 配偶者・子2人 | 配偶者1/2、子2人で1/2(各1/4) |
| 配偶者・子なし・両親健在 | 配偶者・父母 | 配偶者2/3、父母で1/3 |
| 配偶者・子なし・両親他界・姉弟あり | 配偶者・姉弟 | 配偶者3/4、姉弟で1/4(半血は取り分が半分) https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0900-00/ |
| 配偶者なし・子(1人)死亡・孫2人 | 孫2人 | 孫が代襲相続で各1/2。再々代襲も可(子系は無制限)。 https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0887-00/ |
| 配偶者なし・子なし・兄A死亡・甥1人 | 妹・甥 | 兄弟姉妹の代襲は甥姪まで(再代襲なし)。 https://www.souzoku-sp.jp/souzokunin/daisyuu-souzoku.html |
| 内縁の妻と長年同居、子・親・兄弟なし | (法定相続人なし) | 内縁配偶者は相続人にならない。遺言や生前対策が必須。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm |
続柄ごとの取り扱い(実子・養子・胎児・非嫡出子・半血兄弟)
「誰が子に当たるか」「どの兄弟か」によって、相続人となるか・割合が異なることがあります。相続発生前に関係性や書類を確認しておきましょう。
以下では、実務で質問が多い5つの論点をまとめます。
養子(普通養子・特別養子)
養子は養親の法定相続人です。普通養子は実親との関係も残るため、養親・実親双方の相続に関わり得ます。一方、特別養子は実親との関係が終了し、実親側の相続人にはなりません。いずれも養親側では実子と同順位・同割合です。

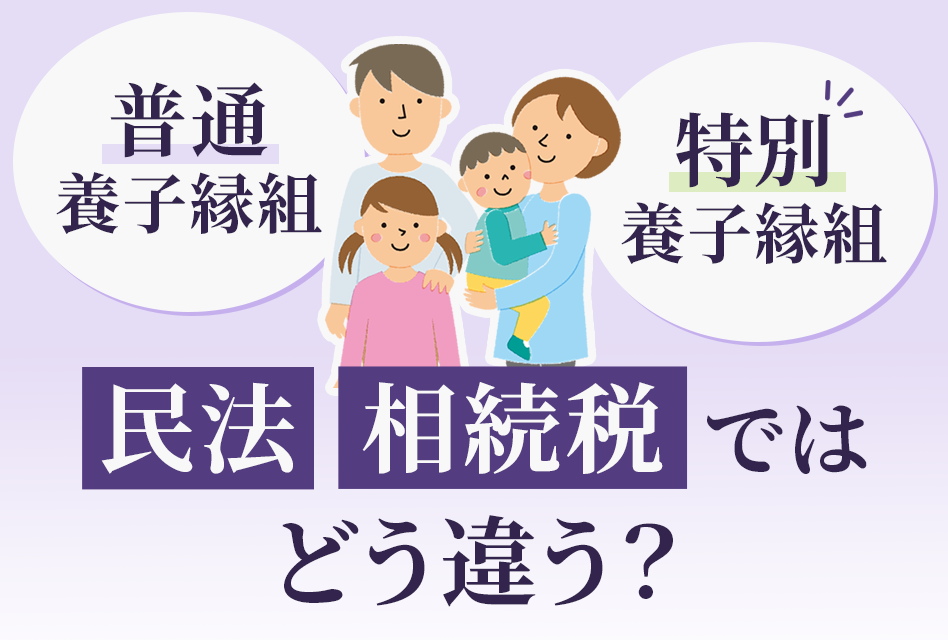
胎児の相続(みなし規定)
胎児は「相続については、すでに生まれたものとみなす」とされ、相続人になります(死産の場合を除く)。配偶者と胎児がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。
非嫡出子(婚外子)の相続分
現在は嫡出子と同等の法定相続分です(2013年の最高裁大法廷決定を受けた民法改正)。認知などの手続は実務上重要です。https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2013/130904.html
半血兄弟姉妹の取り分
父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の1/2です(民法900条4号ただし書)。
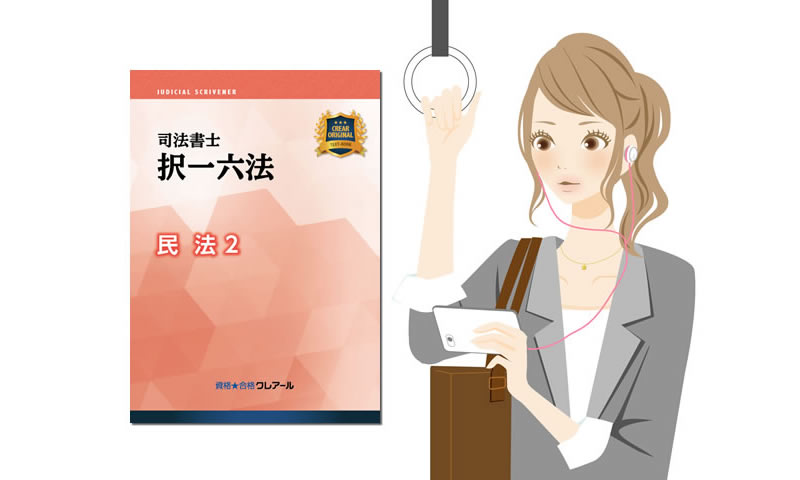
事実婚・同性パートナー
法的婚姻がなければ法定相続人ではありません(自治体のパートナーシップ制度は現行民法の相続権を付与しない)。遺言・生命保険受取人指定・生前贈与・家族信託などでの備えが必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm
相続分の調整:遺言・遺留分・代襲の基礎
遺言があれば、その指定が原則優先されますが、配偶者・子・直系尊属には遺留分があり、偏りが大きい場合は「遺留分侵害額請求」で調整され得ます(兄弟姉妹に遺留分はなし)。
また、相続人が先に死亡・欠格・廃除のとき、子系統では再代襲が無制限に認められますが、兄弟姉妹系統の代襲は甥姪一代限りです。相続放棄は代襲原因ではない点も併せて覚えておきましょう。
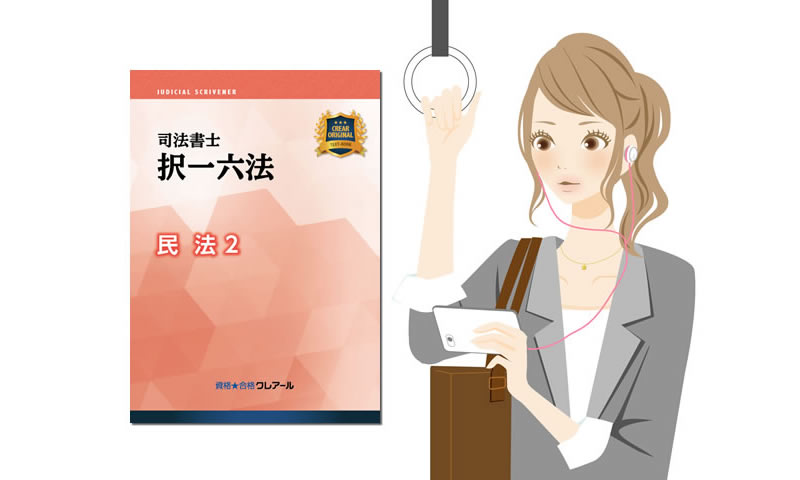
チェックリスト:自分のケースを素早く判定
□ 配偶者の有無(法律婚)/ 子の有無(実子・養子・認知)
□ 子が死亡・欠格・廃除の場合の代襲(孫→ひ孫 …)
□ 直系尊属(父母・祖父母)の生存有無 / 兄弟姉妹(全血・半血)の有無
□ 胎児の有無(相続みなし規定)/ 事実婚・同性パートナーの備え(遺言 等)
□ 法定相続分の確認(900条)と、遺言・遺留分・生命保険等での調整
迷ったら、家族構成図(続柄・生没・認知)を作り、民法887・889・890・900条と突き合わせるのが近道です。税や登記を伴う場合は、弁護士・司法書士・税理士等の専門家に早めに相談しましょう。
よくある質問(FAQ)
法定相続人の範囲・順位・相続分、代襲相続、養子・胎児・半血兄弟姉妹、事実婚や離婚前後の扱い、相続放棄や遺留分など、実務で迷いやすいポイントをQ&Aで整理しました。
Q1. 誰が法定相続人になりますか?配偶者の位置づけは?
配偶者は常に相続人です。血族相続人は第1順位:子(直系卑属)、第2順位:直系尊属(父母・祖父母)、第3順位:兄弟姉妹の順。ある順位の相続人がいれば、後順位は出番がありません。
Q2. 事実婚・同性パートナーは法定相続人になりますか?
現行民法では法定相続人になりません。遺言、生命保険の受取人指定、生前贈与、家族信託などで備えるのが実務的です。
Q3. 離婚協議中・別居中の配偶者の相続権は?
法律上の婚姻が継続している限り、配偶者は相続人です。離婚成立後は相続権はなくなります。
Q4. 子が先に亡くなっている場合、孫は相続できますか?
できます。子が死亡・欠格・廃除のとき、孫が代襲相続します(さらに曾孫へ再代襲も可)。ただし相続放棄は代襲原因ではありません。
Q5. 子が相続放棄したら、その子(孫)は代襲相続しますか?
しません。放棄は代襲原因ではないため、他の同順位者の取り分が増えるか、子の系統がいなくなれば次順位(直系尊属→兄弟姉妹)に移ります。
Q6. 胎児や非嫡出子、養子の取り扱いは?
胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされ相続人になります(死産は除く)。非嫡出子は嫡出子と同等の相続分です。養子は養親側で実子と同順位・同割合です(特別養子は実親側の相続権が原則消滅、普通養子は実親側も残る)。
Q7. 兄弟姉妹に「半血(父母の一方のみ同じ)」がいる場合の相続分は?
兄弟姉妹が相続人となる場面で、半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2です。
Q8. 法定相続分は固定ですか?遺産は自由に分けられますか?
法定相続分は合意不能時等の基準です。共同相続人全員の合意(遺産分割協議)があれば、法定割合と異なる分け方も可能です。遺言で配分指定もできますが、遺留分への配慮が必要です。
Q9. 兄弟姉妹に遺留分はありますか?
ありません。遺留分があるのは配偶者・子(直系卑属)・直系尊属です。
Q10. 連れ子(配偶者の前婚の子)に財産を残したい場合は?
その子を法定相続人にするには養子縁組が必要です。養子縁組をしない場合でも、遺言(遺贈)で財産を渡すことは可能です。
Q11. 兄弟姉妹の代襲相続はどこまで可能?
甥・姪までの一代限りです(甥姪の子への再代襲はありません)。
Q12. 相続人がいない・わからない場合はどうなりますか?
家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、公告等の手続後、特別縁故者への分与を経て残余は国庫に帰属します。
Q13. 相続放棄や限定承認の期限は?延長できますか?
原則、相続開始と相続人を知った時から3か月(熟慮期間)です。事情により家庭裁判所へ期間伸長の申立てが可能です。
Q14. 半血兄弟姉妹と全血兄弟姉妹が混在する場合の按分は?
兄弟姉妹全体の取り分(例:配偶者と兄弟姉妹なら全体で1/4)を、全血:半血=2:1の比で按分し、同種間は均等割します。
Q15. 今日すぐにやるべき確認は何ですか?
①家族構成図(続柄・生没・認知・養子)を作る、②配偶者の有無と子系統の状況(死亡・欠格・廃除・放棄)を整理、③遺言の有無を確認——この3点です。

